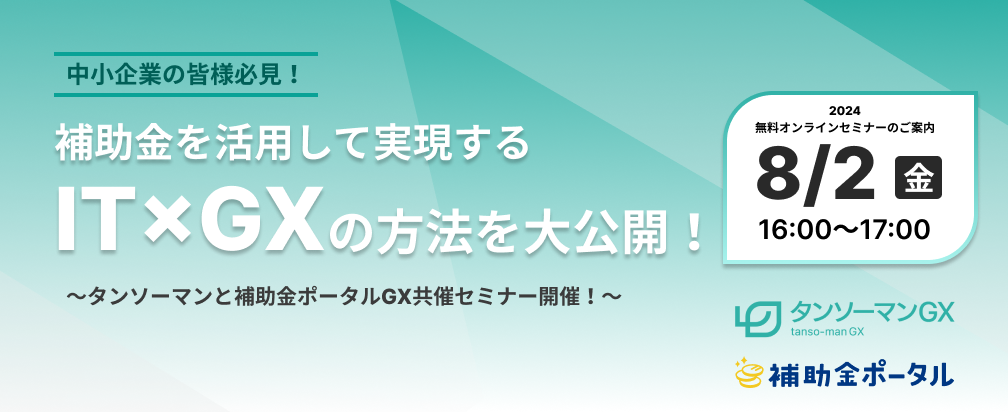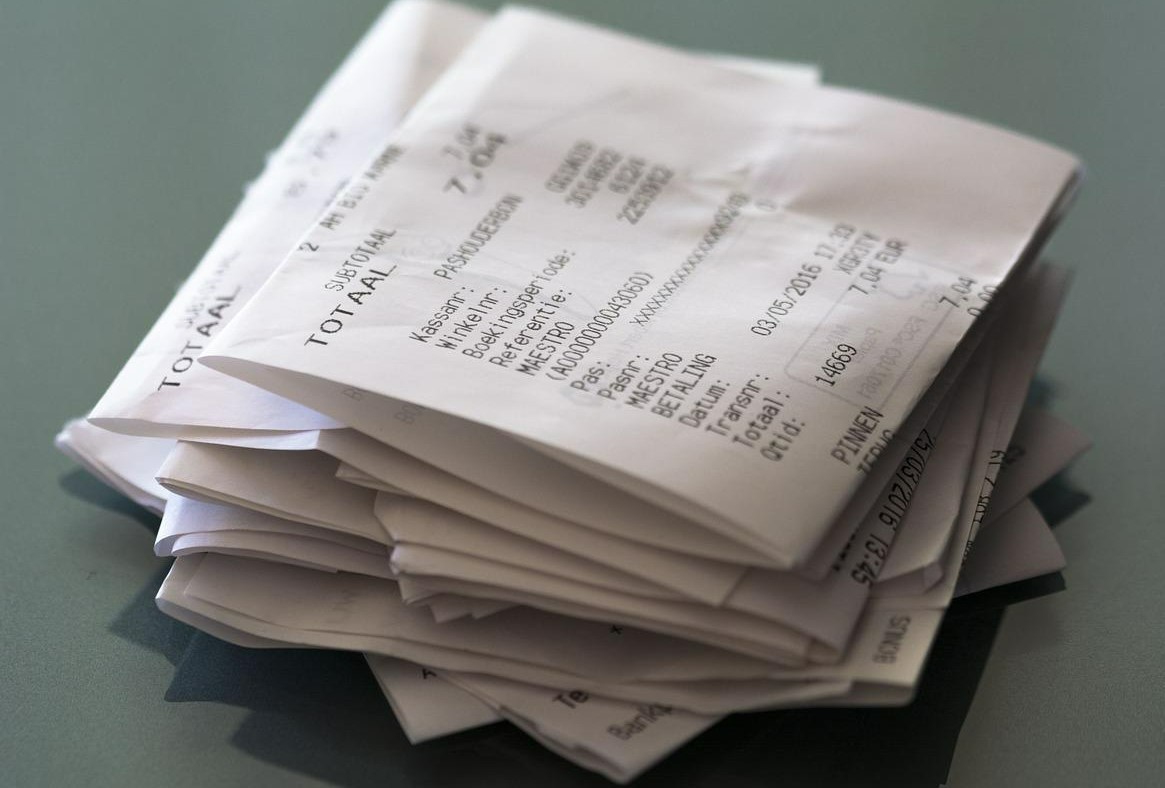
まもなく導入されるインボイス制度によって、これまで課税事業者だった方はもちろん、免税事業者も大きな影響を受けます。特に免税事業者は今後の取引継続に関わる制度なので、そのまま免税事業者を維持するのか、課税事業者へ切り替えるのか、お悩みの方も多いのではないでしょうか?
この記事では、インボイス導入における課税事業者・免税事業者それぞれが利用できる相談窓口や支援策について紹介します。インボイス制度への対応で不安を抱いている事業者は、ぜひ参考にしてください。
▼▼▼日々配信中!無料メルマガ登録はこちら▼▼▼
メルマガ会員登録する
この記事の目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を使用して仕入税額控除を受けるための制度です。取引上の消費税額と消費税率を正確に把握するのが目的で、2023年10月1日より実施される予定となっています。
インボイス制度が求められるきっかけとなったのは、令和元年に導入された軽減税率です。これにより8%と10%の税率が混在する状況になり、適格請求書による正しい消費税納税額の算出が必要になりました。
インボイス制度に関する相談窓口
インボイス制度に関して、下記の窓口で経営相談対応・専門家派遣・講習会の開催等を設けています。- 商工会
- 商工会議所
- よろず支援拠点(中小企業・小規模事業者の経営に関する相談へ対応するため、国が全国に設置している無料経営相談所)
※中小企業119(中小企業庁の専門家派遣事業)を通した専門家派遣も可能です。
免税事業者を維持する皆様への支援
インボイス制度導入にあたり、免税事業者(課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の法人や個人事業主)は適格請求書の発行が可能な課税事業者になるかどうかを任意で選択します。
免税事業者を維持する場合は、取引先の課税事業者がこちらとの取引で仕入税額控除を受けられなくなるため、コストの負担が増えます。その結果、相手は仕入税額控除を受けられる課税事業者との取引を優先し、免税事業者との取引を停止したり、価格の値下げを要求されたりする可能性があります。
このような免税事業者の取引上の懸念に対し、中小企業庁では下記の取り組みを実施しています。
- インボイス制度への対応に関するQ&A
財務サポート「税制」で公表されているQ&Aをご参照ください。
中小企業が抱える取引上のトラブルについて、専門の相談員・弁護士に無料で相談できます。インボイス導入後の免税事業者は、取引減少や価格値下げによる資金繰り悪化が懸念されるため、お悩みの方はこちらの相談窓口をご利用ください。
課税事業者を選択する皆様への支援
インボイス制度で課税事業者になる選択をした場合は、それまで免税扱いだった消費税を納める必要があります。これに伴い、請求書関連や消費税申告に関する業務がより複雑になるため、これらの作業に対応できる仕組みを整えることが重要です。
また、自社が買い手側で取引する際には、取引先に適格請求書を発行できるよう、インボイスに対応した経理システムの導入も求められます。
以下、これらの準備を滞りなく進めるための支援策を紹介します。
(1)デジタル化によるインボイス対応にかかる事務負担の軽減
インボイス対応によって生じる事務負担についての支援策を2点解説します。
【①IT導入補助金】
〈概要〉
中小企業・小規模事業者がITツールを導入する際の経費を補助する取り組みです。
令和3年度補正予算において、インボイス対応を見据えたデジタル化推進を目的とする「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」が追加されました。さらには、令和4年度第2次補正予算で補助下限額が撤廃されたほか、従来のITツールに加えPC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も新たな支援対象となりました。
〈補助対象者〉
中小企業・小規模事業者等
〈申請要件〉
①日本国内で事業を営んでいる。
②申請者の事業場内の最低賃金が、法令上の地域別最低賃金以上である。
③gBizIDプライムを取得している。
④独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が行っている「SECURITY ACTION」の「★一つ星」もしくは「★★二つ星」いずれかを宣言している。
⑤交付申請に必要な情報の入力や、添付資料提出を厳守する。
⑥申請者が管理する携帯電話番号を登録し、事務局からの連絡に応じられるようにする。
⑦事務局へ提出した情報について、国や中小機構が審査・事業管理等の目的で利用することに同意する。
⑧特段の事情がない限りは、事前の調査に協力する。
⑨申請時のログインIDやパスワードは適切に管理し第三者へ渡さない。
⑩補助事業の実施に支障をきたすような訴訟・法令順守上の問題を抱えていない。
⑪補助事業について不正行為を行ったり加担したりせず、また今後も行わない。
⑫補助事業の実施に必要と判断された立ち入り調査等について、要請された場合は協力する。
⑬公募要項の「2-2-2申請の対象外となる事業者」に記載された項目に該当しない。
⑭申請時や事業報告書提出時等に提供した情報について、効果的な支援のために行政機関やその業務委託先等で利用されることに同意する。
〈補助対象経費〉
- ソフトウェア購入費
- クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)
- ハードウェア購入費
- 導入関連費(ソフトウェアの更新等保守サポート費含む)
〈補助額・補助率〉
| ツール名 | ITツール(※) | ITツール(※) | PC・タブレット等 | レジ・券売機等 |
| 補助額 | ~50万円以下 (下限を撤廃) |
50万円超~350万円 | ~10万円 | ~20万円 |
| 補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | 1/2以内 |
(※)会計ソフト・受発注システム・決済ソフト・ECソフト
詳細はIT導入補助金2022(令和3年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)公募要項 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)をご参照ください。
【②みらデジ】
〈概要〉
みらデジは「みらデジ経営チェック」を活用し、インボイス対応を含めた自社のデジタル化状況や経営状態を可視化するポータルサイトです。これにより、経営に有益な情報収集や支援機関などへの相談を実現し、デジタル化による会社の未来をサポートします。
〈経営課題解決までの流れ〉
1.自社の経営課題やデジタル化への取り組み状況について「みらデジ経営チェック(無料で利用可能)」で確認します。
2.保存された「みらデジ経営チェック」の結果をベースとして、みらデジ事務局の専門家から、デジタル化取り組みへのアドバイス・補助金などの施策・ITツール機能等の改善策を紹介されます。
3.改善策が決まったら、専門家のアドバイスを活かし経営課題解決に取り組みます。また、情報収集のためのみらデジ知恵袋も用意されています。
4.経営課題が解決されたら、その後の状況をもう一度「みらデジ経営チェック」で確認することも可能です。もし新たな課題が見つかったら、再度ご相談いただけます。
〈活用事例〉
静岡県の島田掛川信用金庫では、経済団体と始動させた「地域中小企業DX推進プロジェクト」の中核としてみらデジを取り入れました。みらデジ経営チェックにより、事業者は課題と感じていなかった事業承継が今後の重要テーマであると認識し、DX推進と並行して取り組みました。
また、みらデジを活用したDXスキームは、若手職員の躍進を実現しています。若手職員は新しいツールへの適応力が速いことから高評価へとつながり、結果としてさらなるモチベーションアップが生まれています。
詳細はみらデジ公式ホームページをご参照ください。
(2)課税転換に伴う販路開拓支援
次に、インボイス発行事業者への転換を検討している免税事業者へ、おすすめの補助金を解説します。
【小規模事業者持続化補助金】
〈概要〉
小規模事業者等が経営計画を策定し、販路開拓や併せて実施する業務効率化の取り組みを支援します。取り組みに要する経費を補助することにより、地域雇用や小規模事業者等の生産性向上・持続的発展を図るのが目的です。
なお、令和4年度第2次補正予算より、免税事業者からインボイス発行事業者へ転換する場合に、補助上限を一律で50万円上乗せ(最大250万円補助)します。
〈補助対象者〉
小規模事業者等
〈補助対象事業〉
- 地道な販路開拓等を目的とし、策定した経営計画に基づいて実施する取り組みである。もしくは、販路開拓等の取り組みと併せて実施する業務効率化(生産性向上)を目的とした取り組みである。
- 商工会・商工会議所の支援を得ながら実施する事業である。
〈補助対象経費〉
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含みます)
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪委託・外注費
〈補助率・補助上限額〉
| 申請類型 | 補助上限額 | 補助率 |
| 通常枠 | 100万円 (50万円) |
2/3以内 |
| 成長・分配強化枠 (賃上げや事業規模拡大の取り組み) |
250万円 (200万円) |
2/3以内(一部の類型における赤字事業者は3/4以内) |
| 新陳代謝枠 (創業や後継ぎ候補者等の新たな取り組み) |
250万円 (200万円) |
2/3以内 |
※()内はインボイス転換事業者以外が申請した場合の補助上限額です。
詳細は「令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領」をご参照ください。
まとめ
インボイス制度が導入されると、課税事業者であっても免税事業者であっても、新たな事務負担が増加するでしょう。特に免税事業者から課税事業者へ切り替える場合は、想定外の税負担やコストが求められるかもしれません。
業務効率化のためのシステム導入や経理フローの見直しなど、インボイス制度の実施前にしっかりと備えておきたい事業者は、ぜひ支援策の利用を検討してみてはいかがでしょうか。